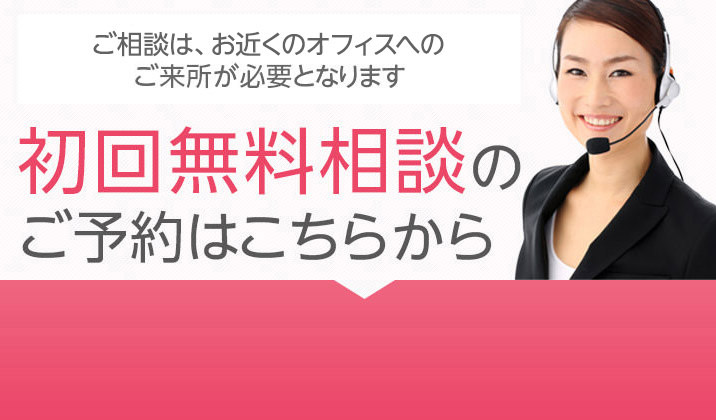婚姻費用と養育費の違い│比較表で相場・内訳を解説
- その他
- 婚姻費用
- 養育費
- 違い

配偶者と別居した場合、自身の収入よりも配偶者の収入が高い場合には、相手に対して生活費、いわゆる「婚姻費用」を請求できます。
民法では、離婚が成立するまでは婚姻費用の支払いを、離婚してからは子どもの養育費の支払いを請求する権利が保障されています。
本コラムでは、婚姻費用と養育費で請求できる内容や期間、金額の決定方法について、ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスの弁護士が解説します。


1、【比較表】婚姻費用と養育費の違い
「婚姻費用」とは、夫婦と未成熟の子どもとの家庭的共同生活を維持していくために必要となる費用のことを指します。
一方、「養育費」とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する子どもの監護や教育のために必要な費用のことを指します。
それぞれ、表で比較しながら具体的な内訳と両者の違いを見ていきましょう。
-
(1)費用の内訳
婚姻費用と養育費の内訳は以下のとおりです。は、夫婦が生活していくために必要な費用であり、具体的には以下のようなものが含まれます。
婚姻費用 養育費 - 衣食住の費用
- 出産費用
- 医療費
- 未成熟子の養育費
- 教育費
- 相当の交通費
- 子どもの衣食住に必要な経費
- 子どもの教育費用
- 子どもの医療費
違いを簡単に説明すると、婚姻費用には、離婚するまでの「配偶者の生活費」および「未成熟の子どもの生活費」が含まれると考えられています。
一方で養育費は、「未成熟の子どもの生活費」のみが含まれます。
婚姻費用について、民法には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定されているため(民法第752条)、夫婦は同居・協力・扶助義務を相互に負っています。そして、夫婦間の扶助については、自己と同程度の生活を保障する義務(生活保持義務)であると考えられています。
養育費について、民法には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されており(民法第877条1項)、このような扶養義務には親から未成熟の子どもに対する扶養義務も含まれていると考えられています。未成熟子の扶養については、配偶者に対する扶養義務と同様、生活保持義務(自己と同程度の生活を保障する義務)が要請されています。 -
(2)費用・相場の違い
裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」をもとに、以下条件の場合における婚姻費用と養育費の相場を紹介します。
ケース1- 夫:年収600万円の会社員
- 妻(親権者):専業主婦
- 子供:2人でどちらも14歳以下
養育費:8〜10万円
ケース2- 夫:年収800万円の自営業
- 妻(親権者):年収300万円の会社員
- 子供:2人でどちらも14歳以下
養育費:14~16万円
なお、婚姻費用と養育費の具体的な金額は個別の事情によって異なるため、あくまで参考としてご覧ください。
- 夫:年収600万円の会社員
-
(3)婚姻費用と養育費の違い
前述の通り、婚姻費用の内訳には養育費も含まれています。そのため主な違いは「誰に対して支払われるか」「いつ支払われるか」という点になります。
婚姻費用 養育費 - 通常、収入の多い方が少ない方に対して
- 離婚が成立するまで
- 子供に対して
- 離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまで(一般的には成人か大学卒業まで)
2、婚姻費用の分担請求ができる期間と決定方法
婚姻費用は夫婦間で発生する費用のため、不足している分については配偶者に請求することができます。請求の根拠や請求期間、金額の決め方について確認しておきましょう。
-
(1)婚姻費用の分担請求とは
民法には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しています(民法第760条)。
そのため、同居している期間のみならず別居している期間についても、離婚が成立するまでは婚姻費用として生活費を分担しなければなりません。
したがって、収入の多い方が他方の配偶者に対して婚姻費用として不足している生活費を支払うことになります。 -
(2)婚姻費用の分担請求ができる期間
婚姻費用を請求できる期間については、原則として「離婚が成立するまで」となりますが、実務上は請求時以降の婚姻費用の支払いしか認められていません。
したがって、別居して以降長らく婚姻費用が支払われていないとしても、過去にさかのぼって婚姻費用を請求することはできません。 -
(3)婚姻費用の決定方法
婚姻費用の決定方法については、原則として夫婦の話し合いによって自由に決めることができます。婚姻費用は、日常生活を維持するために必要となるものですので、月額で決めることが一般的です。
夫婦間の話し合いでは婚姻費用が決められない場合や話し合いができない状態になっている場合には、家庭裁判所に婚姻費用の調停または審判を申し立てることになります。
調停では家事調停員を介するとはいえ、当事者間で話し合いをすることには変わりませんが、好きな金額を請求・約束できるわけではありません。
婚姻費用については、裁判所のホームページに公表されている「婚姻費用算定表」をベースに算出して、当事者間にある個別具体的な事情などを考慮して判断していくことになります。
3、養育費を請求できる期間と決定方法
令和4年4月に成年年齢が18歳に引き下げられました。そのため、養育費を請求できる期間については注意が必要です。養育費の金額の決め方とあわせて確認していきましょう。
-
(1)養育費の請求期間
養育費を請求することができる期間は、離婚してから子どもが経済的・社会的に自立するまでの期間です。また、離婚するまでの子どもの養育費については婚姻費用の中に含まれているため、離婚までの養育費を負担しなくてよいというわけではありません。
養育費の終期については、民法改正までは20歳が成年年齢だったということや20歳までは子どもが経済的に自立しなくても親が支えるという社会的な状況が存在することから、20歳になるまで養育費を支払うとするケースが多かったと考えられます。
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられても、子どもが20歳になるまでは親が支えるという社会状況に変化はないため、これまでどおり、養育費の終期を子どもが20歳になるまでとすることが多いでしょう。
それでは、令和4年3月31日以前に「子が成年に達するまで」として養育費の支払いに合意されていた場合はどうなるのでしょうか。
この点、法務省の見解では、取り決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからすると、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払い義務を負うことになると考えられています。
養育費の制度趣旨からいえば、子どもが未成熟であって経済的に自立していない場合には、子どもが成年に達したとしても養育費の支払い義務を負うことになり、子どもが大学に進学する場合には、大学を卒業するまでは養育費の支払いを合意することも多いと思われます。
以上のように法改正により解釈に疑義が生じるケースもあることから、今後養育費の合意をする場合には、「22歳に達した後の3月まで」といった形で期間の終期を定めることが望ましいでしょう。 -
(2)養育費の決定方法
養育費の決定方法についても、原則として夫婦の話し合いによって自由に決められます。
話し合いでは合意に至らない場合には、子どもを監護している親から他方の親に対して家庭裁判所に調停または審判の申し立てを行い、養育費の支払いを求めていくことになります。
離婚調停の申し立てに伴って離婚後の養育費について話し合いたいという場合には、「夫婦関係調整調停(離婚)」を利用することになります。これに対して夫婦が別居中に、子どもの養育費を含む夫婦の生活費の支払いについて話し合いたい場合には、「婚姻費用の分担調停」を利用することになります。
養育費の算定に関しても、婚姻費用と同様に裁判所が公表している「養育費算定表」に基づいて金額をすり合わせていくことになります。
お問い合わせください。
4、婚姻費用・養育費が支払われないときの対処法
別居相手や元配偶者が婚姻費用や養育費を支払わない場合、どのような対処法をとればいいのでしょうか。
-
(1)内容証明郵便を送付し交渉を行う
相手方が支払いに応じない場合には、「内容証明郵便」で婚姻費用などを支払うように請求していくことになります。
内容証明郵便とは、郵便局が郵送物について「いつ」「どのような内容」で送ったかを証明してくれる手続きです。後々の裁判手続において、権利者が支払義務者に支払請求をしたという証拠資料となるため、相手方にプレッシャーを与えることができます。
そのため、内容証明郵便が送られてきたということだけでも、相手方はこれまでの態度を改め真摯に交渉に応じる可能性があります。
しかし、内容証明郵便は書き方が細かく規定されており、ポスト投函などはできず送付の仕方にも注意が必要であることから、弁護士に作成や送付を依頼することをおすすめします。 -
(2)家庭裁判所の調停・審判を利用する
相手方が任意での話し合いに応じない場合や、話し合っても協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続を利用することになります。
調停手続は、家庭裁判所の裁判官1名と家事調停委員2名で組織する調停委員会が夫婦の間に入り、事情を聴取したうえで合意による解決の道を探る手続きです。
調停手続により話し合いがまとまれば、調停調書が作成され、まとまらない場合には裁判官が審判によって判断を下します。
この審判の内容に対して不服のある当事者は2週間以内に即時抗告を求めることができます。この即時抗告により高等裁判所に判断してもらうことができます。
審理の結果、抗告に理由がなく原審判が相当であると認められた場合には、抗告棄却の決定となります。また、抗告に理由があると認められた場合には、原審判が取り消され抗告裁判所が「審判に代わる裁判」を行うことになります。
なお、調停の段階で弁護士に依頼をすれば、有利な交渉を進めるためのアドバイスが得られ、調停の同席も可能です。また調停がまとまらなかった場合でも、弁護士のサポートにより裁判手続への移行がスムーズになります。 -
(3)養育費は公正証書があれば裁判せずに差し押さえができる
養育費の支払いが滞った場合には、直ちに強制執行を受けてもやむを得ないといった内容(これを「強制執行認諾文言」といいます)を、公正証書で取り決めしておけば、調停や審判といった家庭裁判所での手続きがなくとも、直ちに強制執行の手続きを行うことができます。
養育費について公正証書で取り決めをしていても、強制執行認諾文言の記載がなければ公正証書によって強制執行をすることができないため、トラブルを未然に防ぐためにも弁護士に相談することをおすすめします。
お問い合わせください。
お問い合わせください。
5、まとめ
適切な請求時期に適切な金額を請求しなかったがために、本来受け取れたであろう養育費や婚姻費用を受け取れなかったというケースは少なくありません。
婚姻費用や養育費について、適切に支払いを受けたいという方は、離婚やトラブルの解決実績があるベリーベスト法律事務所 奈良オフィスの弁護士にご相談ください。
お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています