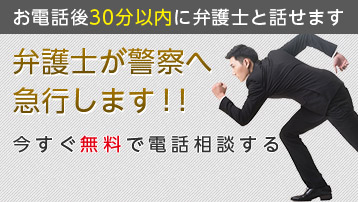名誉毀損で逮捕される場合とは? SNSの悪口は罪になるのか
- その他
- SNS
- 名誉毀損

SNSでついエスカレートして悪口を書き込んでしまったことで、逮捕されたり慰謝料を請求されたりするかもしれない、と不安になっている方がいるかもしれません。
本コラムでは、名誉棄損が成立する要件や、SNSで悪口を書き込むとどのような場合に名誉毀損にあたるのか、逮捕される可能性があるのかなどについて、ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスの弁護士が解説します。


1、名誉毀損罪とは
まずは、名誉毀損が成立する要件や成立しないケース、類似する犯罪との違いなどを解説します。
-
(1)名誉毀損罪の構成要件
構成要件とは、どのような行為がどのような犯罪に該当するかを分類したもので、犯罪が成立するための条件ともいえます。名誉毀損の構成要件の主なポイントは、「公然性」と「事実の摘示」です。
具体的な要件を次に解説します。- 公然性
公然性とは、不特定または多数の人が知り得る状態にあることです。不特定または多数のどちらかを満たせば、公然性が認められます。
不特定または多数が知り得る状態であればよいので、伝えた相手が特定または少数であっても、その少数からさらに他者に伝える可能性があれば公然性が認められる可能性があります。具体的にはSNSでの悪口などです。
一方で、不特定とも多数ともいえない場合は、公然性がないため名誉毀損は成立しません。たとえば、外に声がもれない密室において、本人だけに名誉を毀損するような発言をしても、名誉毀損にはあたりません。 - 事実の摘示
名誉毀損が成立するには、他人の社会的評価を害する事実を示すことが必要です。他人には会社などの法人も含まれ、個人だけでなく法人の名誉を毀損した場合も名誉毀損罪が成立します。
事実とは客観的な真実である必要はありません。つまり、嘘の悪口であっても要件を満たせば名誉棄損になります。
逆に、客観的には真実であっても他人の社会的評価を害する場合には、一定の場合を除いて名誉毀損罪が成立します。
なお、社会的評価を害するような言動でも、それが単なる評価であって事実を示していない場合は、名誉毀損にはなりません。たとえば、「Aさんはいつも気持ち悪い」という発言を不特定多数に発信した場合、「気持ち悪い」という発言は単なる評価であり事実を摘示していないため、名誉毀損にあたりません。
ただし、侮辱罪が成立する可能性はあります。
- 公然性
-
(2)名誉毀損罪が成立しないケース
本来は名誉毀損が成立するケースであっても、表現の自由や知る権利などを考慮して、一定のケースにおいては罰しないことが刑法に規定されています(刑法第230条の2)。
名誉毀損が成立しないポイントは、公共性、公益性、真実性の3つの要件をすべて満たしていることです。- 公共性
公共性とは、摘示された事実が社会的な利益に関わることです。政治家など国の構造に関わる人物の不祥事については、一般に公共性が認められます。
また、有名企業やその経営者など、社会的な影響力が強い団体や人物に関する事実についても、公共性が認められる場合があります。 - 公益性
公益性とは、主として社会的な利益を目的として、事実が摘示されたことを意味します。個人的な恨みや、相手に損害を与えたりすることが目的ではないということです。
事実の公共性が高いほど一般に公益性も認められやすいですが、私怨目的で行われたことが明らかな場合などは、事実の公共性が高くても公益性が否定される可能性があります。 - 真実性
真実性とは、摘示された事実が客観的な真実に合致することです。摘示された内容が真実に反している場合は保護すべき価値が薄いため、名誉毀損が成立するのもやむを得ないということです。
ただし、摘示された事実が真実ではなくても、真実であると誤信し、かつ真実であると信じるのに相当な理由がある場合は、犯罪の故意がないため名誉毀損罪が成立しません。
たとえば、正確な情報を長年提供してきた取材元から汚職の情報を得たため真実と誤って報道し、情報源もそれが真実ではないことを知らなかった場合などは、犯罪の故意がなく名誉毀損罪が成立しない可能性があります。
まずはお気軽に
お問い合わせください。メールでのお問い合わせ営業時間外はメールでお問い合わせください。 - 公共性
-
(3)侮辱罪との違い
名誉毀損と侮辱罪は、どちらも他人の人格を傷つける犯罪ですが、その違いは「事実の有無」にあります。
名誉毀損は、具体的事実を根拠に他人の名誉を傷つける行為です。例えば、「Aさんは盗みをしました」と事実と異なることを公言した場合、名誉毀損に該当する可能性があります。
一方、侮辱罪は、具体的な事実を伴わずに、単に相手を侮辱する言葉をかける行為です。「あなたはバカだ」といった主観的な評価や感情的な言葉は、侮辱罪に該当する可能性があります。 -
(4)信用毀損罪との違い
名誉毀損と信用毀損罪は、どちらも他人の評価を下げる行為ですが、対象となる評価の種類が異なります。名誉毀損は、社会的な評価全般を対象とするのに対し、信用毀損罪は、主に経済的な信用を対象とします。
例えば、以下の具体例でみてみましょう。- 「Aさんは不誠実な人間です」と公言した場合
【名誉毀損】に該当する可能性あり - 「B社の製品は粗悪品で、すぐに壊れます」と事実と異なることを広めた場合
B社の製品に対する経済的な信用を損なうため【信用毀損罪】に該当する可能性あり
- 「Aさんは不誠実な人間です」と公言した場合
2、SNSの書き込みは名誉毀損にあたる可能性がある
前述の通り、名誉毀損の成立に重要なポイントは公然性と事実の摘示ですが、SNSに投稿する場合でもこの2つは成立し得るものです。
まず公然性についてですが、SNSへの投稿はネット上ですぐに拡散する可能性が高いため、不特定または多数が知り得る状態にあり、一般に公然性が認められるでしょう。
次に事実の摘示については、SNSに投稿された発言の内容によります。「芸能人のAは、3年前にBという店で万引きをした」など具体的な事実を含む内容で悪口を投稿した場合は、事実の摘示が認められる可能性があります。
名誉毀損になる例としては、以下のようにSNS上で特定の人物を誹謗中傷する行為が挙げられます。
- 「〇〇さんは窃盗の常習犯だ」と事実無根の情報を拡散する
- 「△△さんは不倫をしている」と具体的な相手を特定して噂を流す
このような行為は、公然と事実または虚偽の事実を指摘し、その人の社会的な評価を低下させる行為といえるため、名誉毀損に該当する可能性が高いです。
一方で、SNS上のDMで「殺すぞ」と言われた場合には、公然性の要件が欠けることになるため、名誉毀損罪は成立せず脅迫罪に問われる可能性があります。
また、「〇〇さんの考え方は理解できない」や「△△さんの作品は好みではない」といった主観的な評価は、事実を指摘しているわけではないため、名誉毀損にはあたりません。
お問い合わせください。
3、名誉毀損で逮捕される可能性はあるか?
名誉毀損で逮捕される可能性はあるのでしょうか。名誉毀損の刑事罰の内容・民事訴訟を起こされる可能性と併せて解説します。
-
(1)名誉毀損罪(親告罪)は告訴が必要
親告罪とは、被害者の告訴がなければ検察官が刑事裁判を起こすこと(起訴)ができない犯罪のことです。名誉毀損や侮辱罪は親告罪です。
したがって、名誉毀損は告訴がなければ起訴の前段階である逮捕も通常は行われません。逆に言えば、被害者が捜査機関に告訴をした場合、名誉毀損で逮捕される可能性があるということです。
告訴とは、犯罪の被害者など告訴をする権利のある方(告訴権者)が、検察官や司法警察員などの捜査機関に対して、犯罪にあった事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示のことです(刑事訴訟法第230条)。
名誉毀損や侮辱については、被害者の利益やプライバシーを保護するため、刑事事件として解決するか、民事事件などその他の方法で解決するかどうかを被害者の意思に委ねています。
また、告訴と似て異なる制度として、被害届があります。被害届とは、犯罪にあった事実を警察署などの捜査機関に申告するものです。なお、告訴するには犯罪事実を特定する必要がありますが、犯人を特定する必要はありません。
告訴と被害届には以下のような違いがあります。告訴と被害届の違い- 告訴は捜査機関が犯罪の捜査をする義務を負うが、被害届は捜査の義務を負わない
- 告訴は犯人の処罰を求める意思表示を含むが、被害届は含まない
-
(2)名誉毀損罪の刑事罰
告訴があれば名誉毀損について捜査が行われ、その結果逮捕される可能性があります。
名誉毀損で逮捕・起訴されて有罪になった場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科されます。
初犯で重い刑罰が科される可能性はあまり高くありませんが、制度上は刑務所に収監される懲役と禁錮の対象なので、名誉毀損は犯罪の中でも比較的重い刑罰といえます。
まずはお気軽に
お問い合わせください。メールでのお問い合わせ営業時間外はメールでお問い合わせください。 -
(3)名誉毀損は民事訴訟の可能性もある
名誉毀損は刑事罰だけでなく、被害者に民事訴訟を起こされる可能性があります。刑事事件と民事事件はそれぞれ別個の手続きなので、被害者は告訴と民事訴訟の両方を行うことができるのです。
民事訴訟を起こされて裁判で負けた場合、逮捕されたり有罪で前科がついたりはしませんが、相手の名誉を傷つけたことに対する損害賠償や精神的な苦痛を与えたことに対する慰謝料などを、金銭で支払うことになります。
損害賠償金や賠償金を支払わない場合は、強制執行の手続きによって給料の口座や資産などを差押えられて、強制的に支払わなければならなくなる可能性があります。まずはお気軽に
お問い合わせください。メールでのお問い合わせ営業時間外はメールでお問い合わせください。
4、名誉毀損トラブルを弁護士へ相談するメリット
名誉毀損に該当するような行為をしてしまった場合、すぐに弁護士に相談するのがおすすめです。名誉毀損について、弁護士に相談すべきメリットや必要性を解説します。
-
(1)名誉毀損に該当するか適切な判断が得られる
名誉毀損が成立するには、公然性や事実の摘示などの要件を満たす必要がありますが、名誉毀損が成立する要件をすべて満たしているかを判断するのは簡単ではありません。
弁護士に相談すれば、SNSへの投稿といった行為が名誉毀損に該当するか、適切に判断できるのがメリットです。また、仮に名誉毀損に該当する場合、具体的にどうすればいいかについて、ケースに沿ったアドバイスを得ることができます。 -
(2)逮捕・起訴の防止につながる
名誉毀損に該当する行為をしてしまった場合、被害者が告訴すれば犯罪の被疑者として逮捕される可能性があります。仮に裁判で有罪になれば、前科がついてしまいます。
名誉毀損などの親告罪で逮捕・起訴を防ぐには、被害者と示談を進めることが重要です。しかし、直接相手側と交渉することは、感情的なやりとりになる可能性もあり、かえって事態の悪化につながりかねません。
弁護士が代理人として冷静に示談交渉することで、相手が告訴する前に円満な解決へと進められることが期待できます。また、すでに相手が告訴してしまった場合でも、検察が起訴するまでに告訴を取り下げる可能性があります。
なお、弁護士は刑事事件だけでなく、被害者が民事訴訟を起こした場合にも対応します。損害賠償請求の訴訟を起こされる前に相手と交渉し、円満な解決が期待できるのも弁護士に依頼するメリットといえます。
5、まとめ
SNSの投稿は不特定または多数の人間に伝わることから、他人の社会的評価を侵害するような悪口を書き込んだ場合、名誉毀損が成立することがあります。
名誉毀損は親告罪なので、告訴を受理した捜査機関には犯罪の捜査をする義務が生じ、逮捕される可能性もあります。また、投稿に内容によっては侮辱罪や信用毀損罪などが成立する可能性もあります。
SNSに悪口を投稿してしまってお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスにご相談ください。刑事事件の弁護士への法律相談は初回60分無料です。解決実績が豊富な弁護士が、逮捕や民事訴訟の対策も含めてトータルにサポートします。
お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています